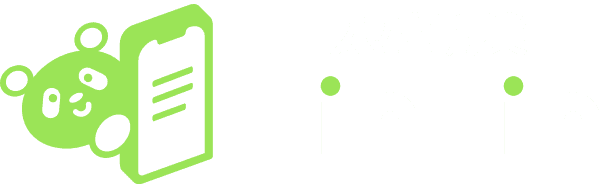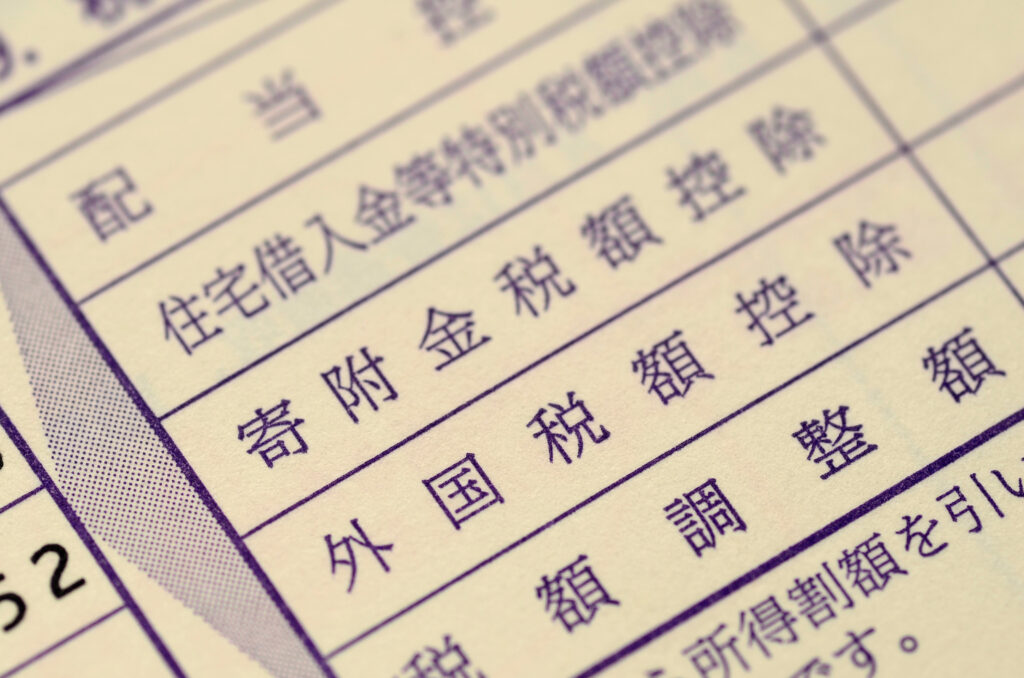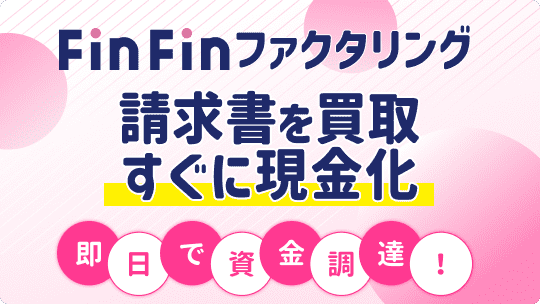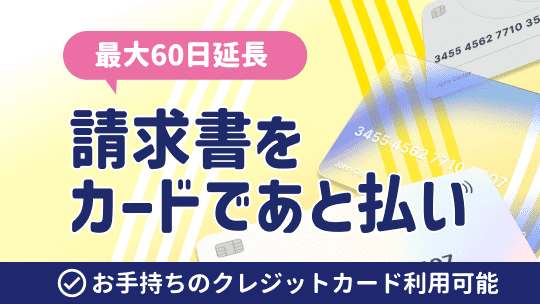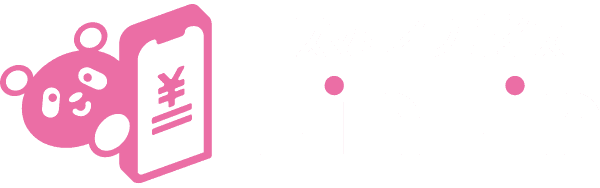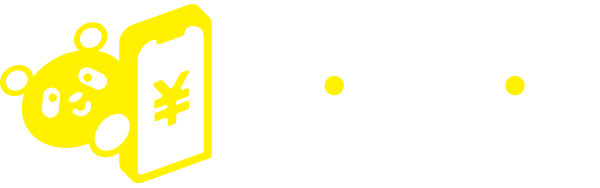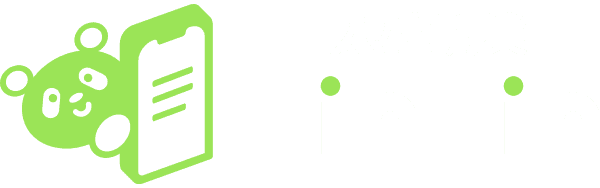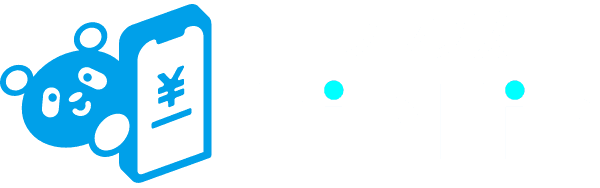領収書の発行方法と保管方法|フリーランスの正しい対応とは?

目次
はじめに:領収書、なんとなくで処理していませんか?
フリーランスや個人事業主として活動を始めると、必ず直面するのが「領収書」の取り扱いです。
「支払いをしたとき、領収書をもらってるけど保管の仕方が不安…」
「逆にお客様から『領収書をください』と言われたけど、どう書けばいい?」
こうした悩みは、確定申告や税務調査のタイミングで一気に重くのしかかってきます。
本記事では、「領収書の正しい発行方法」と「保管のルール」を、実務経験の少ないフリーランスの方でもわかるよう、丁寧に解説します。ミスしやすいポイントやNG例も紹介しながら、「今すぐできる実践法」をご紹介します。
1. 領収書とは何か?なぜ重要?
領収書とは、一言でいうと「代金を受け取りました」という事実を証明する文書です。
個人事業主・フリーランスにとっては、経費の裏付け資料として不可欠な存在です。税務署に経費として認めてもらうためには、支出の正当性を証明する書類(領収書や請求書等)を保管しておく必要があります。
こんなときに「領収書」が必要
- ・事業用のパソコンや文具などを購入したとき
- ・クライアントとの打ち合わせでカフェ代を立て替えたとき
- ・交通費を経費計上したいとき(タクシー利用時など)
2. フリーランスが発行する側になったときの対応
個人事業主として報酬を受け取った際、「領収書を発行してください」と言われることがあります。その際に慌てないよう、必要な記載事項を押さえておきましょう。
領収書に記載すべき基本項目
- ・宛名(例:〇〇 様、〇〇株式会社 御中)
- ・金額(消費税込み/インボイス対応なら内訳記載)
- ・但し書き(例:デザイン業務報酬として、飲食代として)
- ・発行日
- ・発行者の情報(氏名・屋号・住所・電話番号)
- ・収入印紙(※5万円以上の現金取引の場合)
なお、インボイス制度に登録している場合は、「適格請求書発行事業者登録番号」や「税率ごとの消費税額の記載」が必要です。
3. 領収書の保管ルールとNG例
3.1 領収書の保存期間は「原則7年間」
個人事業主は、青色申告でも白色申告でも、帳簿や領収書の保存義務があります。
通常は「7年間」の保存が必要で、特に次のケースでは税務署に提出を求められることがあります。
- ・税務調査の対象になった
- ・還付申告を受けた
- ・記帳内容に不備があった など
3.2 紙と電子、どちらでもOK?
- ・紙で受け取った領収書 → 紙のまま保管(ホチキス留めや日付順でのファイリングが有効)
- ・メールやPDFで受け取った領収書 → 電子ファイルで保管OK(クラウド保存でも可)
※ ただし、「電子帳簿保存法」に対応するためには、要件を満たす形式での保存が必要です(例:改ざん防止、検索機能の確保 など)。
3.3 電子保存の注意点(電子帳簿保存法)
電子的に保存する場合、単にPDFをPCやクラウドに保管するだけでは不十分なケースがあります。電子帳簿保存法では、以下のような要件を満たす必要があります:
- ・タイムスタンプの付与(改ざんされていないことの証明)
- ・検索機能の確保(日付・金額・取引先で検索できる状態)
- ・保存データの見読性(画面上で内容が明確に確認できる)
このため、専用ソフトやアプリを使って管理する方法が安全かつ確実です。
「なんとなくクラウドに入れておく」では、いざ税務署から求められたときに対応できない可能性がある点に注意しましょう。
4. よくあるミス・NG例
①レシートを捨ててしまった
→ レシートでも税務上の証拠になります。レシートも立派な領収書です。
②金額や日付を手書きで改ざんしてしまった
→ 故意でなくとも、修正した履歴が残っていないと信頼性が損なわれます。
③友人からもらった私的なプレゼントの領収書を経費にした
→ 事業と関係のない支出は、経費として認められません。
5. まとめ:領収書の正しい知識はフリーランスの武器になる
「なんとなく保管していた」「書き方がわからないから適当に発行していた」という状態では、いざというときに損をしてしまいます。
個人事業主・フリーランスとして活動するなら、領収書の発行方法と保管方法は”最低限の基礎知識”として身につけておきましょう。
【おさらいチェックリスト】
・発行時は、宛名・但し書き・日付・インボイス番号を忘れずに!
・紙でも電子でもOK。7年間しっかり保存!
・レシートも経費証明になる。小さな支出も捨てない!
領収書管理アプリを活用して、手間とリスクを減らそう
最近では、領収書の発行・保存・インボイス対応までワンストップで管理できるクラウド会計・経費管理アプリも増えてきました。
たとえば「FinFinインボイス」などのアプリでは、テンプレートに入力するだけでインボイス制度に対応した領収書を簡単に発行でき、データ保存も電子帳簿保存法に準拠しています。
- ・発行履歴の自動記録
- ・電子保存の法令対応
- ・税理士との共有もしやすいUI
などの機能があり、特に忙しいフリーランスやスモールビジネスにとっては、手間をかけずに安心して備える手段となるでしょう
整った経理環境は、あなたのビジネスの信頼性にもつながります。
【スマホで簡単】FinFinを使って確定申告をしよう
「領収書まわりをきちんと整えたいけど時間がない」「どのアプリを使えばいいか不安…」という方は、「FinFin」を活用するのもおすすめです。
レシートや領収書を読み込んで手軽に仕訳管理をすることができます。また、質問に答えるだけで確定申告の必要書類が完成します。悩んでいる方はぜひ「FinFin」を試してみてください。
記事執筆者紹介

公共政策GサービスリーガルエキスパートチームTL
税理士
渡邊 亮先生
大学卒業後に4大税理士法人に入所。大手日系企業や外資系企業を中心に税務申告業務及び税務相談業務に従事。その後M&A部門に異動し、上場企業やファンド等を対象にM&A関連業務及びクロスボーダー取引等に関する税務アドバイザリー業務を担当。 2023年8月よりタイミーに参画し、新しい働き方における税制面の課題解決に向けて日々調査研究を行っている。