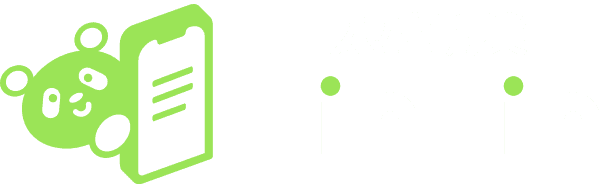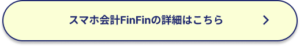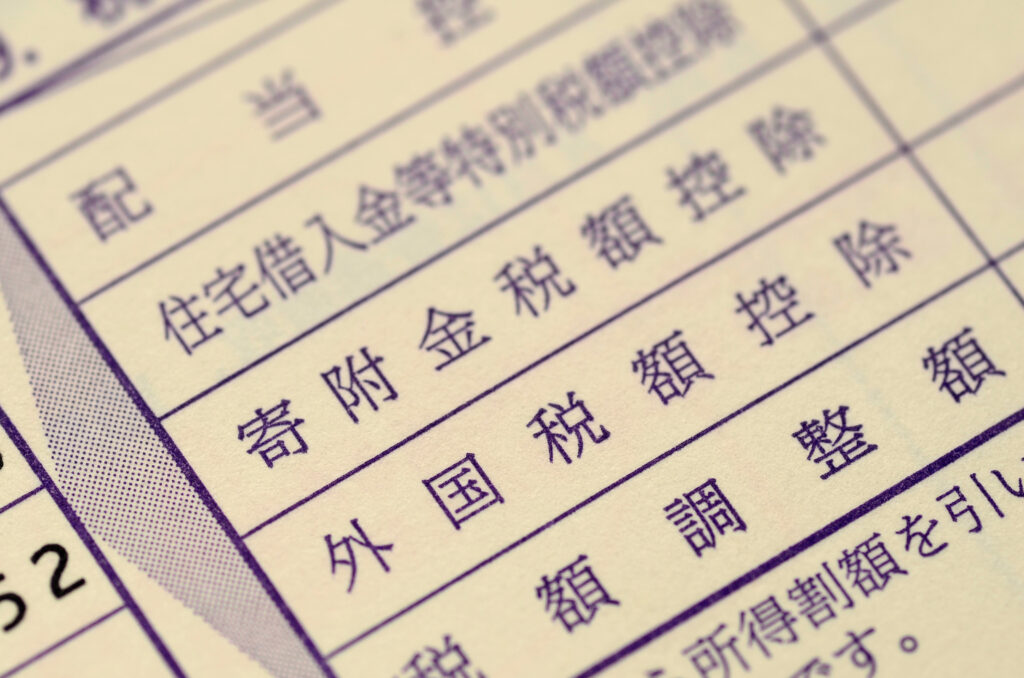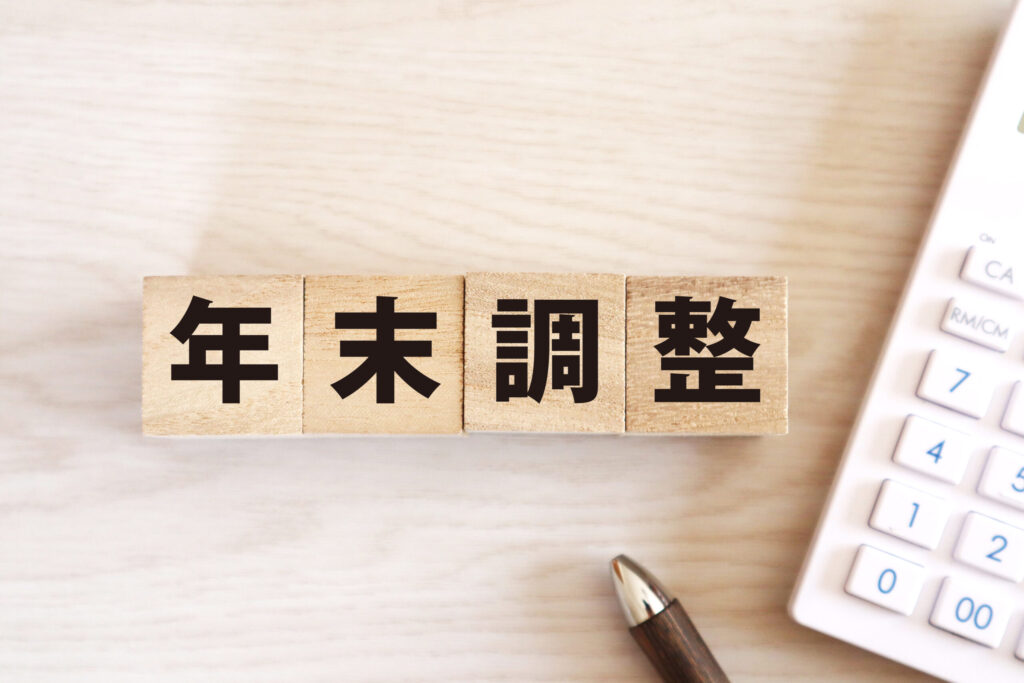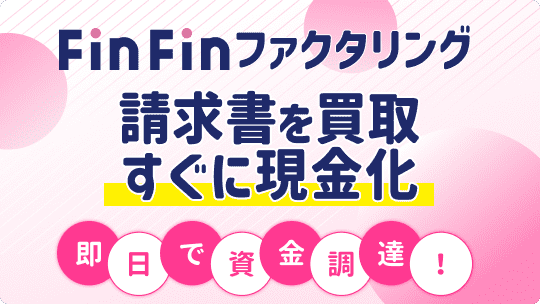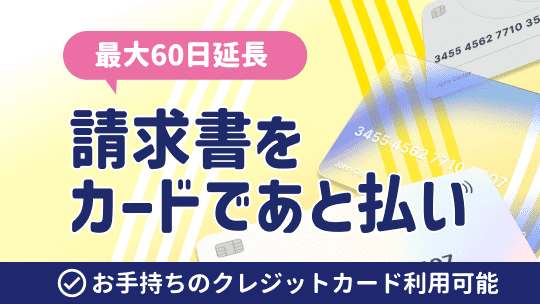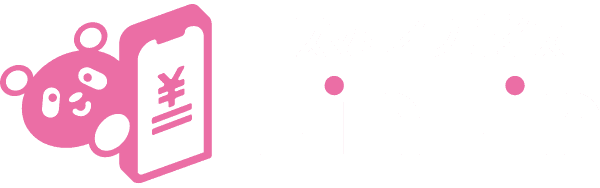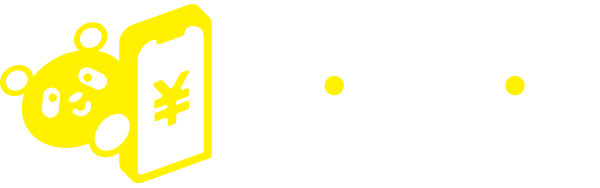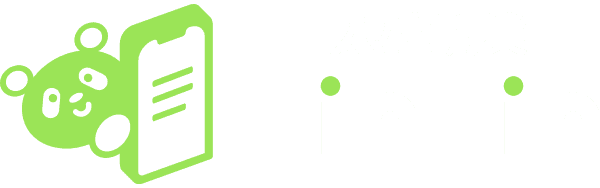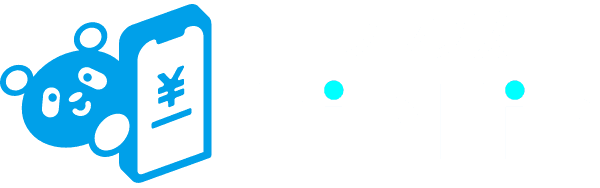年金受給者は確定申告不要? 必要・不要の判断基準や申告で得するケース、申告を忘れたときの対応を解説

「年金を受け取っているから、確定申告は関係ない」と思っていませんか?実は、年金受給者でも条件によっては確定申告が必要なケースがあります。
この記事では、確定申告が必要になる条件や申告を忘れたときのペナルティ・対応方法、さらに申告をしたほうがお得になるケースまで、わかりやすく解説します。「自分も申告が必要なのかよくわからない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
スマホ会計FinFinは、スマホ一つで簡単に確定申告ができるアプリで、レシートの読み取りや口座連携でほとんど自動で仕訳登録ができるため、面倒な作業を効率化して安心して確定申告をすることができます。
目次
1. 年金受給者でも確定申告が必要なケース
年金を受け取っている人の中には、確定申告が必要な人と不要な人がいます。申告の要否は、次の条件で判断できます。
| 確定申告が必要な人 | ・公的年金等の収入金額が400万円を超える場合(2ヶ所以上から受給している場合は合計額) ・公的年金等の収入金額が400万円以下でも、年金以外の所得(給与や投資など)が20万円を超える場合 |
| 確定申告が不要な人 | ・公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の人(源泉徴収等がある場合) |
たとえば、公的年金が420万円あり、株式投資で30万円の利益がある場合は確定申告が必要です。一方で、年金収入が350万円で他に収入がない場合は、申告の必要はありません。また、年金収入は「雑所得」として扱われ、勤務先の年末調整では反映されないため、年末調整後に自分で確定申告を行い、正しい所得税額を算出する必要があります。
確定申告が必要か迷ったら、毎年1月頃に日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」を確認しましょう。この書類の「支払金額」が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
2. 確定申告をしないとどうなる?
確定申告の提出期間は、毎年2月16日~3月15日頃です。この期間を過ぎてしまった場合でも、税務署に申告書を提出すれば受理してもらえますが、ペナルティが発生する可能性があります。
ペナルティの内容
確定申告の期限を過ぎて提出・納税した場合には、延滞税が課されます。また、申告自体をしなかった場合は無申告加算税の対象です。ただし、期限から1ヶ月以内に自主的に申告すれば、無申告加算税はかかりません。気づいたらすぐに税務署へ申告しましょう。
▼無申告加算税の税率
| 区分 | 税率 |
| 納付税額が50万円未満 | 10% |
| 納付税額のうち50万円を超える部分 | 15% |
| 納付税額のうち300万円を超える部分 | 25% |
| 期限後でも自主的に申告した場合 | 5% |
還付申告を利用できる場合も
実は、申告を忘れた場合でも過去5年間までは「還付申告」が可能です。払いすぎていた税金が戻ってくることもあるため、控除の漏れや未申告の年がある方は確認してみましょう。
3. 年金受給者が確定申告をした方が得になるケース
確定申告が不要な人でも、申告をすることで得になるケースがあります。ここでは、代表的なケースをいくつかご紹介します。
①医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除とは、年間に支払った医療費が基準額を超える際、税務署に確定申告することにより、その超過分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。控除額は年収によって異なります。(上限200万円)
・年収200万円未満:(医療費 − 保険金などで補填される金額) − 総所得金額等の5%
・年収200万円以上:(医療費 − 補填金額) − 10万円
また、健康診断や対象市販薬の購入に年間12,000円以上かかった場合は、セルフメディケーション税制で超過分を控除できます。(上限88,000円)
②生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合は「生命保険料控除」、地震保険料を支払っている場合は「地震保険料控除」が利用できます。どちらの控除も、所得税と住民税の計算に反映されます。控除の上限は以下の通りです。
・生命保険料控除:所得税12万円、住民税7万円
・地震保険料控除:所得税5万円、住民税2万5,000円
控除を受けるには、毎年10〜11月頃に保険会社から届く控除証明書の提出が必要です。
③ふるさと納税
ふるさと納税を行った場合も、確定申告が必要になることがあります。ふるさと納税は、自治体に寄付することで税金の控除や返礼品の受け取りができる制度で、自己負担2,000円を超えた分が控除の対象です。ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きが必要です。
④災害や盗難に遭った場合
自然災害や盗難、横領などで、生活に必要な資産(住居や家電など)に損害を受けた場合、雑損控除として所得控除を受けられます。控除額は以下のどちらか多い方で計算されます。
・(損害額 + 災害関連支出 − 保険金など) − 総所得金額等 × 10%
・(災害関連支出 − 保険金など) − 5万円
4. 年金に対して課される税金の計算方法
確定申告をする際、公的年金は「雑所得」として計算します。公的年金に対しては、収入金額に応じた「公的年金等控除額」が差し引かれます。控除額は所得段階ごとに定められており、詳細は国税庁の「公的年金等控除額表」で確認できます。
公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合
| 年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金に係る雑所得の金額 |
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 65歳未満 | 60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-60万円 |
| 65歳未満 | 130万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 |
| 65歳未満 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 |
| 65歳未満 | 770万超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 |
| 65歳未満 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 65歳以上 | 110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額-110万円 |
| 65歳以上 | 330万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 |
| 65歳以上 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 |
| 65歳以上 | 770万円超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 |
| 65歳以上 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 |
公的年金等の雑所得以外の所得が1,000万円超かつ2,000万円以下の場合
| 年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金に係る雑所得の金額 |
| 65歳未満 | 50万円以下 | 0円 |
| 65歳未満 | 50万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-50万円 |
| 65歳未満 | 130万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-17万5,000円 |
| 65歳未満 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-58万5,000円 |
| 65歳未満 | 770万超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-135万5,000円 |
| 65歳未満 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-185万5,000円 |
| 65歳以上 | 100万円以下 | 0円 |
| 65歳以上 | 100万円超330万円未満 | 収入金額の合計額-100万円 |
| 65歳以上 | 330万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-17万5,000円 |
| 65歳以上 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-58万5,000円 |
| 65歳以上 | 770万円超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-135万5,000円 |
| 65歳以上 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-185万5,000円 |
公的年金等の雑所得以外の所得が2,000万円超の場合
| 年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金に係る雑所得の金額 |
| 65歳未満 | 40万円以下 | 0円 |
| 65歳未満 | 40万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-40万円 |
| 65歳未満 | 130万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-7万5,000円 |
| 65歳未満 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-48万5,000円 |
| 65歳未満 | 770万超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-125万5,000円 |
| 65歳未満 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-175万5,000円 |
| 65歳以上 | 90万円以下 | 0円 |
| 65歳以上 | 90万円超330万円未満 | 収入金額の合計額-90万円 |
| 65歳以上 | 330万円超410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-7万5,000円 |
| 65歳以上 | 410万円超770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-48万5,000円 |
| 65歳以上 | 770万円超1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-125万5,000円 |
| 65歳以上 | 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-175万5,000円 |
※引用:公的年金等の課税関係(国税庁)
5. スマホ会計FinFinなら、ミスなく安心して確定申告が可能!
「スマホ会計FinFin」は、年金受給者や給与所得者、フリーランスや副業者など、確定申告を行うすべての人に対応したアプリです。スマホだけで日々の会計管理から確定申告の作成・提出まで完結でき、入力ミスや計算漏れを防ぎながら、簡単かつ安心に申告作業を行える設計が特長です。
副業・事業者モードが選べる
スマホ会計FinFinには、お客様の働き方に応じた2種類のモードを用意しています。
・副業かんたんモード
会社勤務で副業をしている方(個人事業主を除く)やパート・アルバイトの方向け。お持ちの源泉徴収票を読み取るだけで、簡単に確定申告ができます。
・事業者モード
開業届を提出している方や個人事業主・フリーランスの方向け。日々の仕訳登録から確定申告までのすべての機能が利用できます。
仕訳の自動化を実現
レシートや領収書をスマホで撮るだけで、適切な勘定科目を推定して自動で仕訳登録。さらに、銀行口座やクレジットカードと連携すれば手間なく記帳ができ、作業時間と入力ミスを大幅に削減します。
確定申告初心者でも操作しやすい
始めて確定申告を行う方や会計用語が分からない方でも、画面内のヘルプや説明文を見ながら作業できるため安心。ハードルの高い書類作成や仕訳登録なども、アプリ内の質問に答えていくだけで、自動で必要な申告書類を作成できます。
マイナポータル連携で必要な情報が自動反映
マイナポータルとの連携により、主たる給与の源泉徴収票や医療費通知における必要情報が自動で申告書へ反映されるため、確定申告が必要な会社員の方や医療費控除を検討している方の申告の手間が大幅に削減できます。
6. まとめ
年金受給者でも、特定の条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。また、申告不要な場合でも控除や還付を受けられるケースがあり、申告を行うことで結果的に得をすることがあります。
そんなときに役立つのが「スマホ会計FinFin」です。マイナポータルとの連携機能により、医療費通知などの確定申告に必要な情報を自動で申告書に反映できるほか、ふるさと納税のポータルサイトで発行される、ふるさと納税の寄付金控除に関する証明書をアプリで取り込むことができます。
来年の確定申告シーズンに向けて早めに準備を整え、安心して年金生活や副業に集中できる環境を作りましょう。
7. よくある質問
Q. 年金受給者でも確定申告は必要ですか?
年金収入が年間400万円を超える場合、または年金以外の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。申告不要の条件でも、医療費控除やふるさと納税などの控除を利用すると、確定申告によって還付金を受け取れることがあります。年金受給者でも控除や還付を受ける場合は、申告を検討しましょう。
Q.確定申告の準備が不安です。簡単に申告できる方法はありますか?
「スマホ会計FinFin」を使えば、日々の会計業務から確定申告までスマホ一つで完結できます。さらに、マイナポータルと連携することで医療費通知が自動で申告書に反映され、面倒な手入力や計算ミスを防ぎながら、簡単に確定申告を完了できます。
Q.申告不要でも確定申告をするメリットはありますか?
はい、医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税などの控除を受けたい場合や、過払い税金の還付を受けたい場合は申告がおすすめです。年金受給者でも、申告することで払いすぎた税金が戻り、結果的に得をすることがあります。