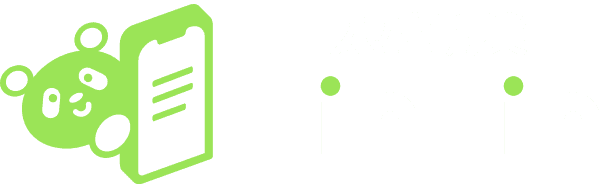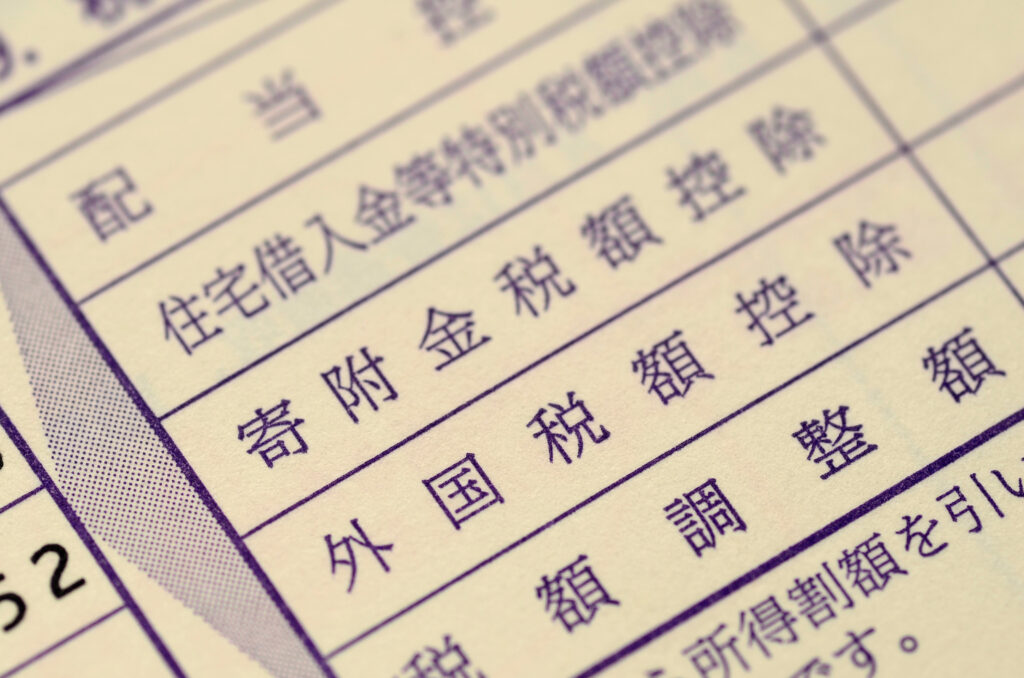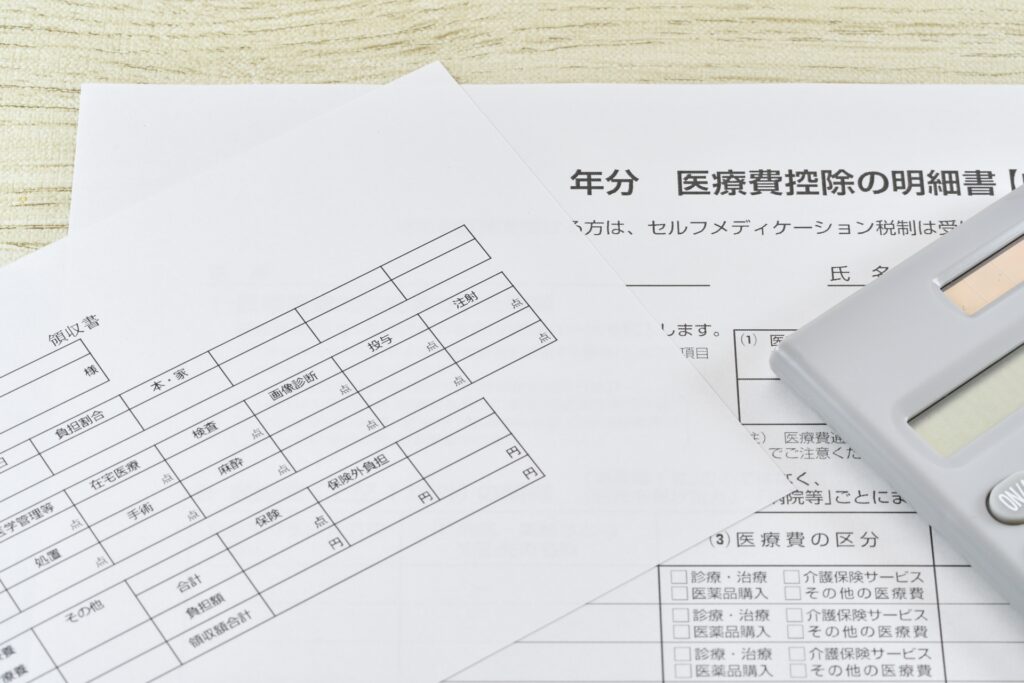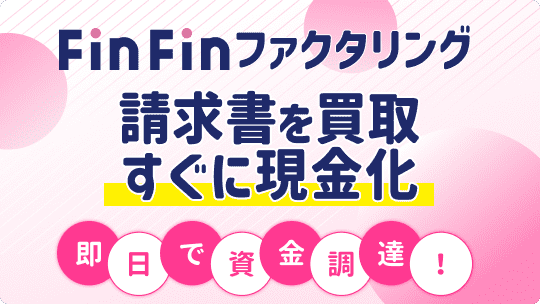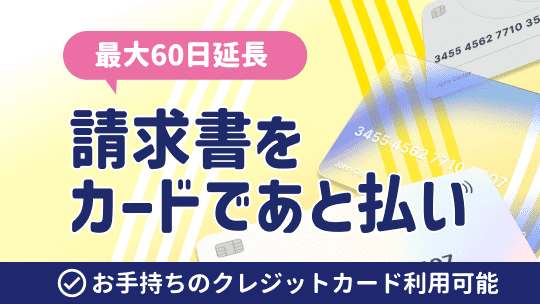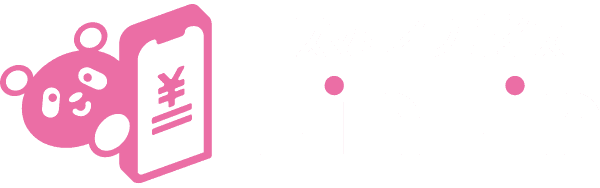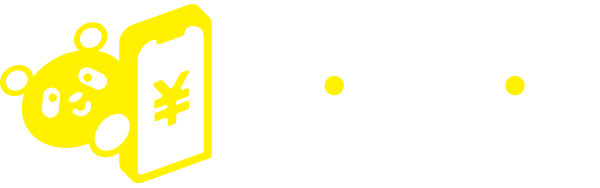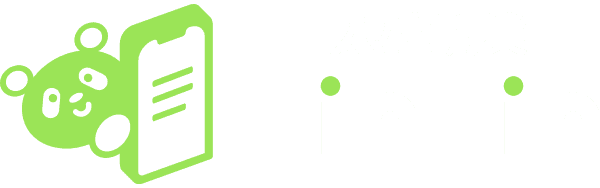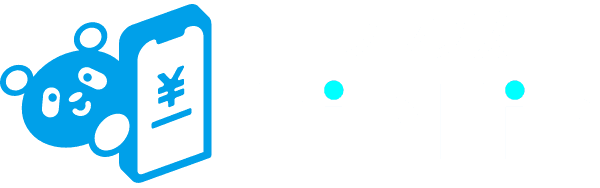【確定申告 初めての方必見】
確定申告とは?なぜ必要?自分で簡単にできる方法までやさしく解説!

「確定申告」と聞くと、「なんだか難しそう」「自分には関係ない」「税理士に頼むもの」と感じていませんか?特に初めて確定申告をする方にとって、その複雑な手続きや専門用語は大きな壁のように思えるかもしれません。しかし、副業やフリーランスが当たり前になった今、確定申告は決して他人事ではありません。実は、確定申告の本質や目的を理解すれば、誰でも簡単に、そして自分自身で完結できるしくみが整っています。
この記事では、「確定申告とは?」という基本的なことから、なぜ自分で申告する必要があるのか、そして歴史的な背景まで、初めて確定申告に挑む方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、確定申告への漠然とした不安がなくなり、自分にとって必要な手続きかどうかを判断できるようになっているでしょう。
目次
1. 確定申告とは?―その目的と歴史的背景
確定申告とは、1年間の所得(もうけ)を計算し、それに対する納めるべき所得税の額を国に申告・納税する手続きのことです。所得と税金の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間。原則、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
このしくみは、日本では明治時代に始まります。当初、税金の徴収は国が強制的に行っていましたが、所得の多様化や経済の発展に伴い、国が個々人の正確な所得を把握することが困難になっていきました。そこで、納税者自身に所得を計算させて申告させる「申告納税制度」が整備・導入されました。つまり、確定申告は国に強制されるものではなく、“自分の所得や税金は自分で申告する”というのが大原則になっているです。
2. あなたは対象者?確定申告が必要な人のチェックリスト
初めて確定申告をする方が最も気になるのは、「自分は確定申告が必要なのか?」という点でしょう。以下のチェックリストに当てはまる方は、原則、確定申告が必要です。
| 給与所得者(お勤めの方) | □ 年間の給与収入が2,000万円を超える
□ 2か所以上から給与をもらっている □ 副業の所得が年間20万円を超える |
| 個人事業主やフリーランス | □ 事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を上回る |
| 年金受給者 | □ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える
□ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える |
| その他 | □ 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
□ 不動産や株式などを売却し、売却益が出た □ ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除などで還付を受けたい |
3. 収入と所得はどう違う?
① 収入
会社からもらった給与や、商品が売れて入ってきた売上金など、手元に入ってきたお金の総額です。
② 所得
収入から「必要経費」を差し引いて残った、自分の利益(もうけ)のことです。確定申告では、基本的にこの所得に対して税金がかかります。
4. 必要経費とは?申告で使える費用の考え方
必要経費とは、事業を行う上で「必要だった支出」のことです。収入を呼び込むためにかかった支出、つまり業務を行う上で直接的に関わった支出をいいます。たとえば、フリーランスのデザイナーであれば、パソコン代、ソフトウェアの購入費、デザイン関連の書籍代などが該当します。自宅を仕事場にしている場合は、家賃や電気代の一部も経費にできます(白色申告の場合は一部制限あり)。経費を正確に計上することで、所得が減り、結果として納める税金を抑えることができます。これらを正しく記録・証明できる証拠書類(領収書や請求書など)と帳簿が重要になります。
5. 確定申告の基本的な流れと提出方法
① 1年間の取引を記録し、決算をする
収入と経費を帳簿につけて記録し、青色申告決算書または収支内訳書を作成し、所得を導きます。
② 所得控除・税額控除を確認する
社会保険料控除・扶養控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除について適用の有無を確認する。特に2025年度の税制改正において基礎控除の適用額、扶養控除における被扶養親族等の所得要件が変更され、また特定親族特別控除が創設されているのでご注意ください。
<所得控除等の改正について>
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
② 申告書類を作成する
帳簿書類をもとに、確定申告書を作成します。
③ 書類を提出する
作成した申告書・青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を税務署に提出します。現在はe-Tax(電子申告)が主流です。
④ 納税・還付
所得税を納めるか、源泉徴収などで払いすぎた税金の還付を受けます。
6. 確定申告をしないとどうなる?
もし確定申告が必要なのに申告を忘れたり、故意に怠ったりすると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。無申告加算税は納めるべき税額の15~30%、延滞税は年率2.4~8.7%(2025年基準)と決して軽視できない金額です。また、悪質な場合は重加算税(無申告の場合は40%)が課される可能性もあります。期限内に正しく申告することが、余計な負担を避ける最も賢い選択です。
7. 初めてでも安心!確定申告をスマホで簡単に完結できるFinFin
「帳簿づけや申告書類作成はやっぱり難しそう…」と感じた方におすすめしたいのが、『FinFin』です。『FinFin』は、初めて確定申告をする方のために開発された、シンプルで使いやすいスマホアプリです。
① スマホひとつで完結
銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引データを自動で取り込み、帳簿を自動で作成してくれます。
② 専門知識は不要
「これは経費になるの?」という疑問にも、チャット形式で答えてくれるサポート機能が充実していますので、特に個人事業主やフリーランスにとってとても便利です。なお、複式簿記の知識がなくても青色申告の要件を満たすような帳簿処理もできます。
③ かんたん申告
必要な情報を入力するだけで、確定申告書が自動で完成。そのままe-Taxで提出することも可能です。ちなみに『FinFin』はインボイス制度にも対応しており、請求書の発行や管理にも対応しています。
まとめ
税金の手続きは、これからますます“自分ごと”として身近になる時代へと変わっていきます。納税の未来はさらにスマートになります。国が推進する税務行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)により、e-Taxの利用はますます拡大し、将来的には個人事業主にもe-Taxが義務化されるでしょう。また、マイナポータル連携による自動入力機能の充実が進み、確定申告に必要な情報が自動で揃うしくみが整ってきています。こうしたデジタルインフラの進化により、申告書をイチから手書きする時代は過去のものとなり、数回のクリックやタップで申告が完了する未来が現実のものになろうとしています。つまり、確定申告は「難しいもの」から、「日常の延長」で自然に処理される存在へと変わりつつあるのです。
今、確定申告に関心を持ったあなたは、これからの“納税の未来”を先取りしている存在ともいえるかもしれません。確定申告を正しく行うことは、自分自身の家計管理にもつながる大切な習慣です。初めて確定申告に挑む方にとって、まずは「自分は対象かどうか」を把握することが第一歩。そして、その先の複雑な作業は、スマホアプリ『FinFin』のような便利なツールを取り入れておくことで、格段にラクになります。ぜひ、スマートな納税の第一歩を踏み出しましょう。
記事執筆者紹介

西原憲一先生 西原会計事務所
大阪市生まれ。大阪市立大学商学部卒。2000年に独立。
税理士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
法人・個人の税務会計、資産運用、相続・事業承継設計などマネー全般の実務に携わる。各種セミナー講師、書誌やWebでの執筆・監修など、全国で活動中。