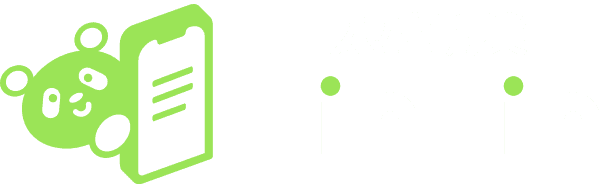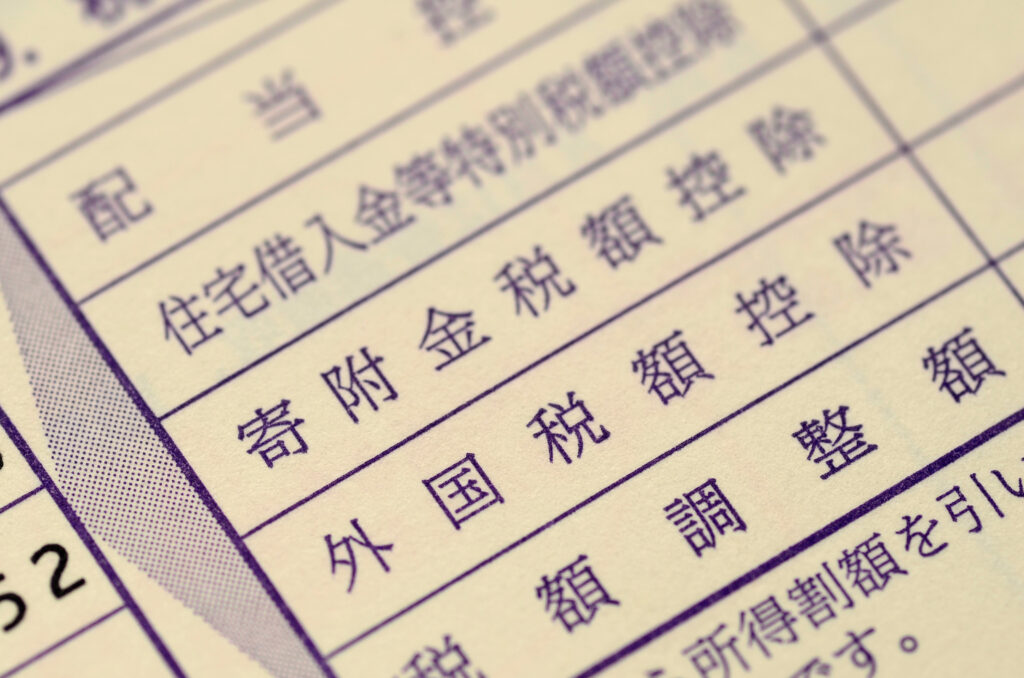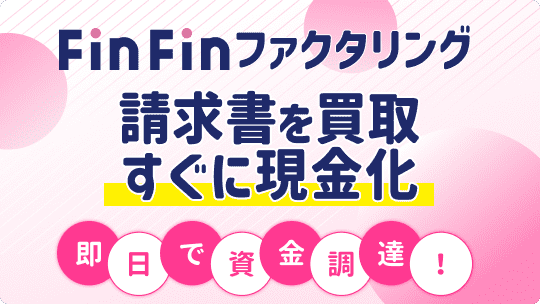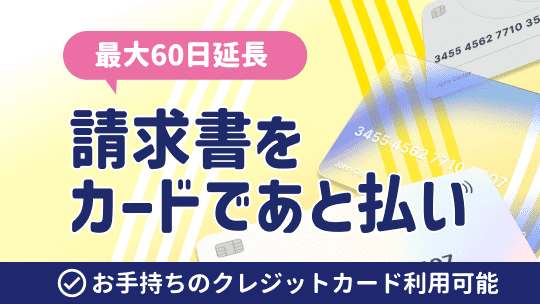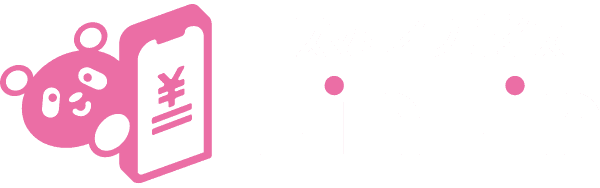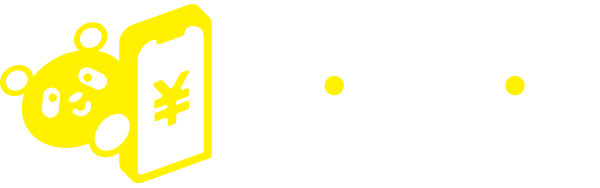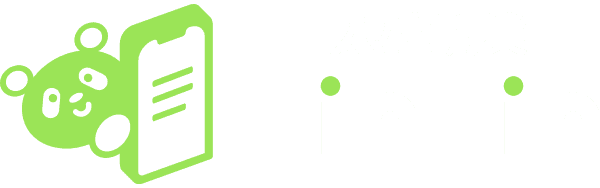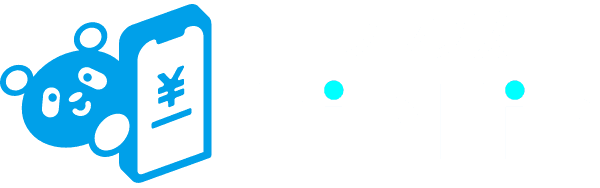個人事業主の開業後に必要な税務手続きとは?提出書類・期限・やることリストを徹底解説

開業届を提出したものの、「この後何をすればいいの?」と戸惑い、思わずパニックに…。
そんな“開業ハイ”の余韻に浸っている間にも、現実は容赦なく押し寄せてきます。税務署への書類提出や帳簿の管理、確定申告に向けた準備などやるべきことは山積み。そんな時はどうしても焦ってしまいがちですが、ご安心ください。今回の記事では、個人事業主が開業後に行うべき税務手続きを「やることリスト」として整理しつつ、専門的な内容もわかりやすく解説します。記帳や申告は会計アプリを活用すれば、あなたの事業スタートがぐっとラクに。あの“ややこしい書類”も、まるっとカバーします。
目次
1.開業届を出したらどうするの?その後やるべき税務手続き
開業届を提出したら「さあスタートだ!」と勢いよく踏み出したくなるもの。ですがその前に、個人事業主として最初に済ませておくべき“税務署への書類提出”があります。これを忘れてしまうと思わぬ損をしたり、後々面倒なことになったりする可能性もあるので要注意です。
| 申請・届出書類の名前 | 詳細 | 期日 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺可能 | 原則、開業日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員に給与を支払う場合は源泉徴収義務が発生するため、適切な届出で税務署からの指摘を防ぐ必要がある | 従業員を雇い始めてから1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員が10人未満の場合、源泉所得税の納付回数を年2回に減らすことが可能。1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月20日までが納期となり、納付の手間が大きく軽減。人手が少ない個人事業主にとっては非常に有効 | いつでも申請可能。原則、申請した日の翌月に支払う給与から適用 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 登録することでインボイス(適格請求書)を発行できるようになり、取引先が仕入税額控除を受けられるようになる。特に法人や課税事業者との取引がある場合、登録していないと取引先の負担が増え、今後の仕事に影響する可能性も。信頼性を保ち、継続的な取引を円滑に進めるためにも、登録は大きなメリットがある。なお、この申請をすると必ず消費税の申告・納税が必要であることに注意 | 免税事業者が納税義務の免除を受けない課税期間に登録を受けようとする場合、登録を希望する課税期間の初日から起算して15日前までに申請書を提出する必要がある。
(例)免税事業者が令和7年6月1日に登録を希望する場合、申請書には登録希望日を令和7年6月1日と記載し、令和7年5月17日までに提出しなければならない |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の申告で簡易課税制度を選ぶと、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、原則課税方式ではなく簡易課税方式を選択できる。簡易課税制度では、業種ごとの「みなし仕入れ率」に基づいて納税額を計算できるため、記帳負担が軽減され、申告業務が簡素化される。ただし、この制度を選択した場合、最低2年間は継続して適用する必要がある | 適用を受けようとする課税期間の前日まで |
このように開業後に提出すべき税務手続きの書類は多岐にわたりますが、提出のタイミングと内容さえしっかり押さえておけば、それほど臆することはありません。特にインボイス制度や簡易課税制度は、うっかりしていると申請のタイミングを逃してしまい、後からは選べなくなってしまうことも。事業スタートのタイミングでこうした手続きをまとめて済ませておくことで、その後の運営がぐんとラクになります。いずれの申請も、e-Taxを使えば自宅や外出先から手軽に提出できるので、早めの対応がスムーズな事業運営のカギになります。
2.確定申告で慌てない!開業後すぐに始めるべき準備とは
確定申告は、1月から12月までの所得を翌年2~3月に申告するビッグイベント。ですが、年末に焦って帳簿を整えようとしても時すでに遅し…というのが“事業者あるある”なのです。
ならば、すぐにでも始めるべき準備は次のとおりです。
・売上・経費の帳簿作成(収支内訳書や青色申告決算書)
・レシートや領収書の保管
・必要経費にできる支出の事前チェック
・自宅兼事務所(事業所)の家賃や水道光熱費の「事業用按分」処理の準備
節税のコツは「経費をもれなく記録」「証憑をちゃんと保管」することです。ですが、「記帳が面倒すぎて大変!」という方もいるのではないでしょうか。そんな方は、ぜひ次の章をご覧ください。
3. “帳簿迷子”にならない!会計アプリで自動化ライフ
手書きで帳簿をつけたり、表計算ソフトで管理する方法もありますが、ミスや手間を考えると手作業での管理はあまり現実的ではありません。会計アプリを導入すれば、おそらく日々の会計処理の90%以上は自動化できるでしょう。
・銀行口座やクレジットカードと連携 ⇒ 自動仕訳が可能
・領収書や通帳の情報を取り込んで入力 ⇒ 帳簿や決算書が自動で作成
・確定申告書類を直感的に簡単作成 ⇒ インターネット上で電子申告できる
初めての作業でも、使いやすいUIとガイド機能で迷わずに操作できます。「ちょっと試してみたいな」と思ったら、まずは無料体験版から気軽に始められるのも嬉しいポイントです。
4.よくある質問と回答
Q.税務署にはいつ行けばいい?
A.各種申請書・届出書を提出期限内に税務署窓口へ提出しましょう。e-Taxによる電子申請も可能です。
Q.売上が少ない年も確定申告は必要?
A.所得(売上から必要経費を差し引いたもの)が基礎控除以下の場合は不要です。しかし、赤字を翌年以降に繰り越したいのであれば、青色申告事業者として確定申告しなければなりません。
Q.会計アプリの費用は経費にできる?
A.はい。年間利用料や導入費用は「通信費」や「業務委託費」などとして必要経費に算入できます。
5.【保存版】やることリスト
☑ 青色申告承認申請書の提出(2か月以内)
☑ 給与支払事務所の届出(従業員を雇う場合)
☑ 源泉所得税の納期特例申請(従業員10人未満の場合)
☑ インボイス登録申請(課税事業者になる場合)
☑ 消費税簡易課税制度選択届出書の提出(申告をラクにしたい場合)
☑ 会計アプリを導入し、自動記帳をスタート
☑ 収入・経費の請求書や領収書を必ず保管
☑ 自宅兼オフィスなら按分処理も忘れずに
開業後はバタバタしがちですが、事業の土台を整えることが長期的な成功への鍵になります。今すぐ「やることリスト」をチェックしながら、確実かつスムーズなスタートを切りましょう!
【スマホで簡単】FinFinを使って開業届を提出しよう!
開業を考えたら、まずはこのアプリ!「スマホ開業FinFin」は、個人での開業を目指す方にぴったりのアプリです。開業届や青色申告承認申請書の作成・電子申請まで、すべてスマホひとつで完結!シンプルな操作で、書き方がわからない方でも安心して使えます。まずは一度お試しください!
記事執筆者紹介

西原憲一先生 西原会計事務所
大阪市生まれ。大阪市立大学商学部卒。2000年に独立。
税理士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
法人・個人の税務会計、資産運用、相続・事業承継設計などマネー全般の実務に携わる。各種セミナー講師、書誌やWebでの執筆・監修など、全国で活動中。