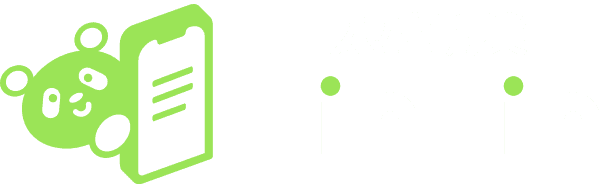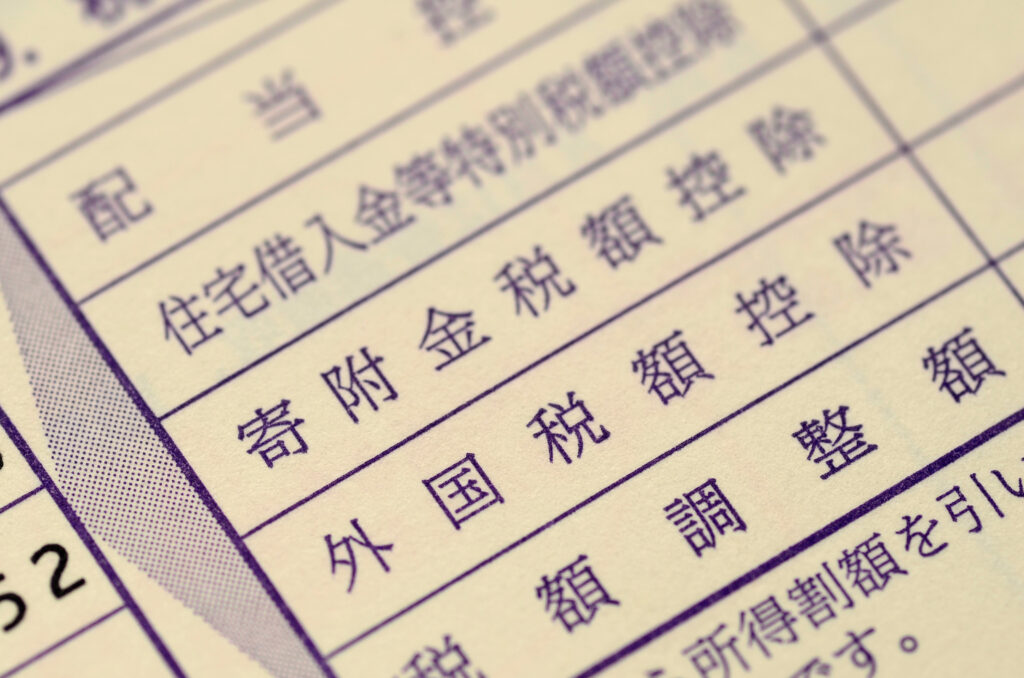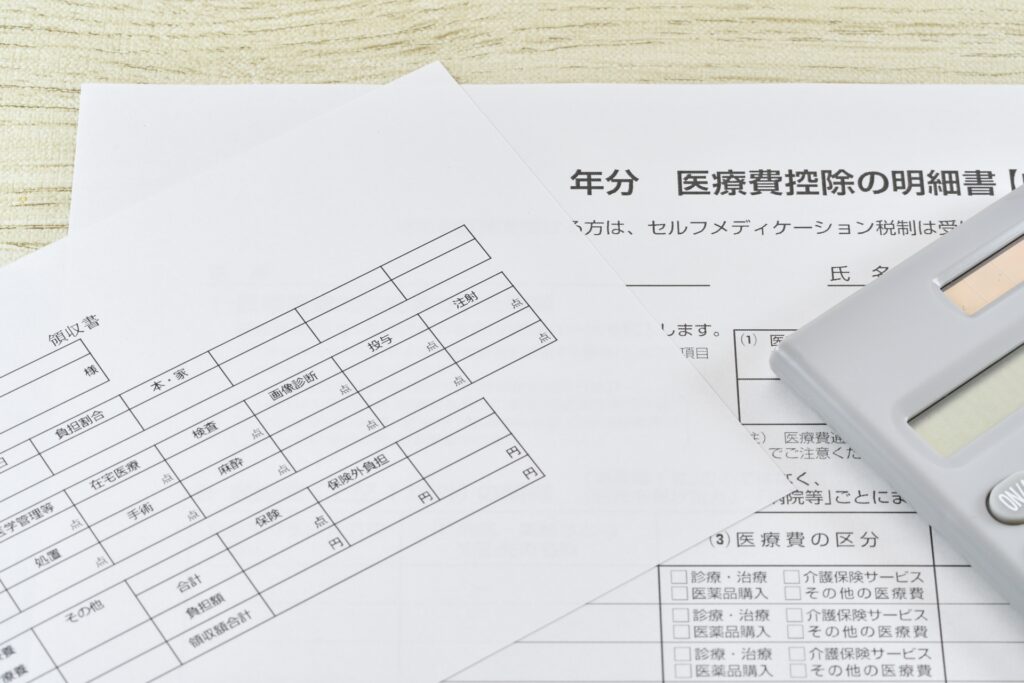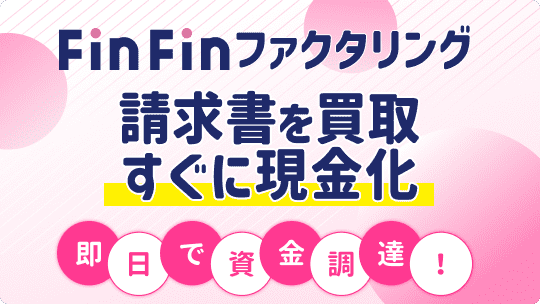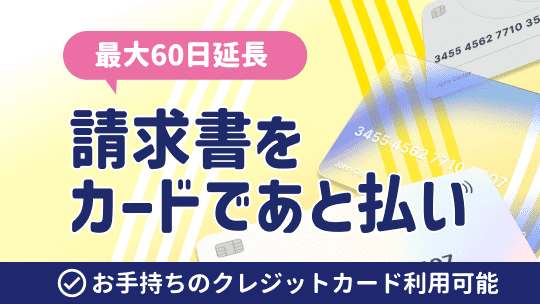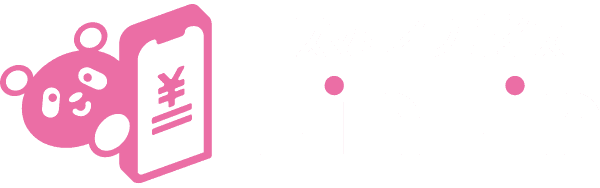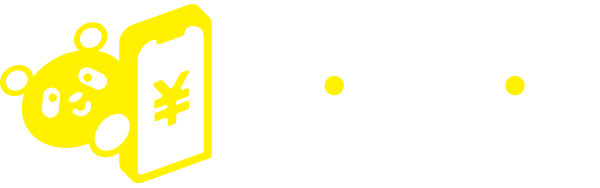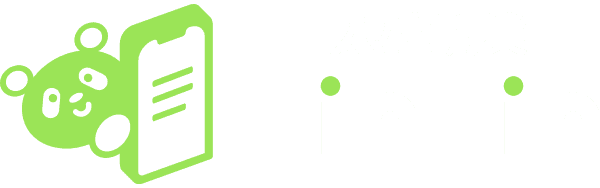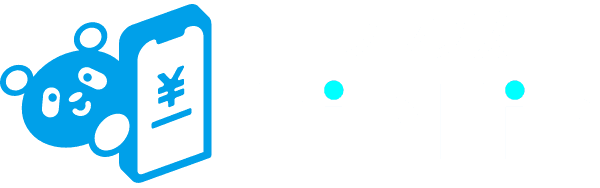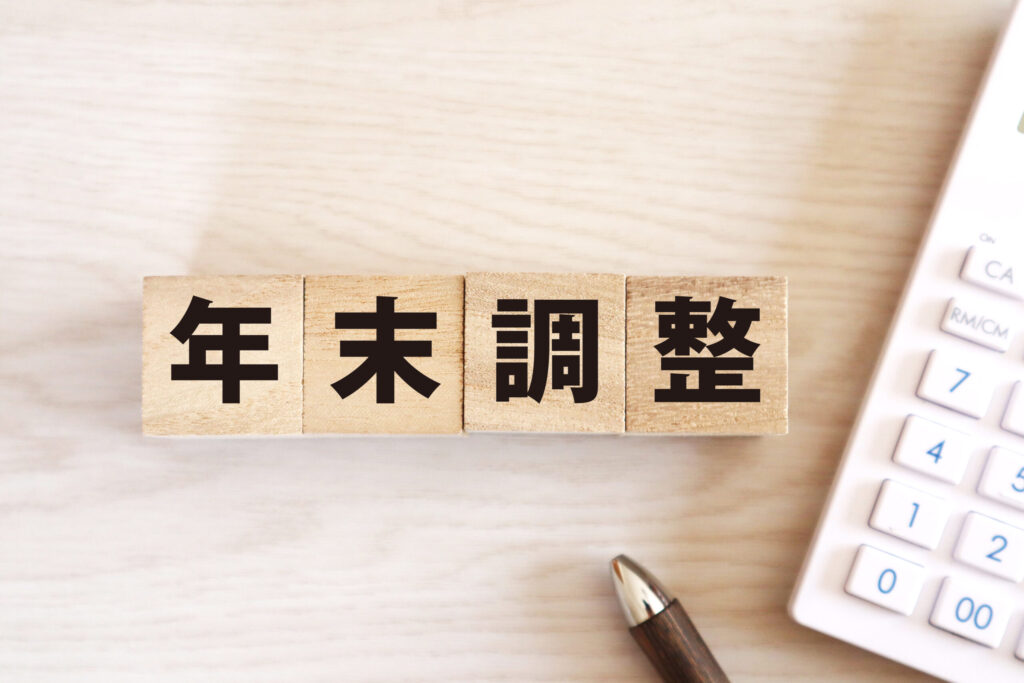
会社員や公務員の給与所得者は、毎月の給与から源泉徴収された所得税を、年末にまとめて精算する「年末調整」という手続きを受けます。実際の作業は秋頃から始まり、従業員が書類を提出するタイミング、会社が税務署へ提出するタイミングなど、時期ごとに行うべき内容が明確に決まっています。この記事では、年末調整がいつ始まり、どの書類を、どのタイミングで準備すべきなのかをスケジュール形式で詳しく紹介します。
また、会社員でも年末調整だけで完結せずに確定申告を行うケースがあります。そんな時はスマホ一つで簡単に確定申告ができる「スマホ会計FinFin」がオススメです。源泉徴収票の読み取りだけで確定申告が必要かどうかをチェックできる「かんたんモード」を用意しているほか、ふるさと納税や医療費控除などの控除申請だけに集中して確定申告を行える「控除だけモード」も搭載しています。
目次
1. 年末調整とは
年末調整は、1年間の給与に対して源泉徴収されてきた所得税を、年末に正しい税額へ調整するための仕組みです。給与支給時に差し引かれている源泉所得税はあくまで概算のため、年間の所得額や控除額が確定する年末に、会社が従業員の代わりに税額を再計算し、過不足を精算します。
従業員が行うことは、①必要書類への記入と②保険料控除証明書などの原本を添付し、会社へ提出することの主に2点です。
年末調整の対象となる従業員
年末調整の対象となる従業員は、主に次のような方々です。
| 年末調整の対象となる人 | 年末調整の対象とならない人 |
| (1)1年を通じて勤務している人 (2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人 (3)年の中途で退職した人のうち、次の人 ①死亡により退職した人 ②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が123万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) (4)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) |
(1)左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2)左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者) (4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人 (5)非居住者 (6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) |
2. 年末調整はいつ行われる?年間スケジュールを公開
年末調整は、その年の10月から翌年1月の間に進められます。従業員と会社側で行うことが異なるため、全体像を把握しておくと非常にスムーズです。
| 時期 | 会社側の作業 | 従業員の作業 |
| 10月~ | ・年末調整の書類を配布 | |
| 11月 | ・書類の回収・内容確認 | ・各種申告書や控除証明書の記入・提出 ・前職の源泉徴収票の提出 |
| 12月 | ・税額計算と精算(還付または徴収) ・年末調整の最終処理 |
・精算結果の確認 |
| 翌年1月 | ・年末調整関係書類の提出 ・住民税関係書類の提出 ・源泉徴収票の提出 |
対象となる給与
「その年の1月1日〜12月31日までに支払われた給与」が対象です。精算の結果、税金を払い過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収となります。
※12月分の給与が翌年1月支払いの場合は、翌年分の年末調整の対象になります。
3. 従業員が提出する書類と提出期限
一般的に提出期限は11月に設定されますが、会社によって異なるためご自身で勤務先へ確認するようにしてください。
従業員が会社に提出する書類は以下の通りです。控除を受けるには、生命保険料や地震保険料などの控除証明書の添付が必須です。証明書は例年10月頃に保険会社から届くため、年末調整まで紛失しないよう保管しましょう。
| 全員が提出 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
| 該当者のみ提出 | ・給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書 ・住宅借入金等特別控除申告書 |
提出が遅れた場合
万が一、証明書を紛失したり、申請が間に合わないなどで提出が遅れてしまった場合でも、会社が1月末までに法定調書を提出できれば年末調整に反映される場合があります。しかし、提出が遅れ過ぎると年末調整で控除が適用されず、自分で確定申告が必要になることもあります。
提出後の修正はいつまでできる?
書類を提出した後に訂正したくなった場合は、翌年1月31日までなら会社で対応してもらえる可能性があります。ただし、源泉徴収票が発行された後は会社側での修正が難しくなるため、早めに相談しましょう。
また、2月以降に誤りに気づいた場合や源泉徴収票の発行後に修正が必要になった場合は、従業員自身が確定申告で修正する必要があります。
4. 還付・追加徴収はいつ行われる?
年末調整の結果として発生する還付や追加徴収は、多くの場合「12月の給与」に反映されます。還付金は12月の給与へ上乗せされるケースが一般的で、逆に税金が不足していた場合は、12月または1月の給与から追加徴収されることが多いです。会社によっては別日に振込が行われたり、現金で支給される場合もあります。
なお、正確な金額は12月の給与明細や年末調整後に配布される源泉徴収票で確認することができます。
還付が発生しやすい主なケース
年末調整で還付金が発生するのは、1年間で源泉徴収された所得税の総額が、実際に支払うべき税額より多かった場合です。一般的には、最終的に納めるべき税額は源泉徴収額より少なくなることが多く、多くの人が還付を受ける傾向にあります。
さらに、年末調整の際に各種の所得控除や税額控除を申告することで、還付金が増えることもあります。これらの控除が適用される主なケースとしては、次のようなものがあります。
| ・生命保険・医療保険へ加入している(生命保険料控除) ・扶養家族が増えた(扶養控除) ・iDeCoに加入している(小規模企業共済等掛金控除) ・住宅ローン控除を返済している(住宅借入金等特別控除) ・社会保険料を個人で支払った(社会保険料控除) |
5. 確定申告が必要になる主なケース
会社員であっても、年末調整だけでは完結しないケースがあります。主に以下のような場合は年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要です。
| ・副業(給与以外)で20万円を超える所得がある ・年収が2,000万円を超えている ・年の途中で退職し、その後再就職していない ・医療費控除・寄附金控除・特定支出控除などを受ける予定がある ・住宅ローン控除の初年度である |
6. 確定申告が必要なら、スマホ会計アプリ「FinFin」がオススメ!
医療費控除や寄附金控除、副業での収入など、年末調整では完結しないケースに該当する方は確定申告が必要です。しかし、確定申告は書類の準備から申告書への記入、書類提出まで対応しなければならず、毎年時間がかかってしまいがちです。
そこで役立つのが、確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」です。スマホだけで確定申告書の作成・提出まで完結でき、入力ミスや計算漏れを防ぎながら、スムーズに確定申告を行えます。確定申告が必要な方は、申告シーズン前の今のうちにインストールすることをオススメします。
自分の働き方に合わせたモードを選べる
スマホ会計FinFinには、お客様の働き方に応じた3種類のモードを用意しています。
・事業者モード
開業届を提出している方や個人事業主・フリーランスの方向け。日々の仕訳登録から確定申告までのすべての機能が利用できます。
・かんたんモード
会社勤務で副業をしている方(個人事業主を除く)やパート・アルバイトの方向け。お持ちの源泉徴収票を読み取るだけで、簡単に確定申告ができます。
・控除だけモード
ふるさと納税や医療費控除などの必要な控除だけに集中して効率よく申告したい方向け。支払った医療費や購入した医薬品の合計金額などを入力するだけで、医療費控除額とセルフメディケーション税制を利用した場合にいくらお得になるかをシミュレーションできます。
仕訳の自動化を実現
レシートや領収書をスマホで撮るだけで、適切な勘定科目を推定して自動で仕訳登録。さらに、銀行口座やクレジットカードと連携すれば手間なく記帳ができ、作業時間と入力ミスを大幅に削減します。
確定申告初心者でも操作しやすい
始めて確定申告を行う方や会計用語が分からない方でも、画面内のヘルプや説明文を見ながら作業できるため安心。ハードルの高い書類作成も、アプリ内の質問に答えていくだけで、自動で必要な申告書類を作成できます。
マイナポータル連携で必要な情報が自動反映
マイナポータルとの連携により、主たる給与の源泉徴収票や医療費通知における必要情報が自動で申告書へ反映されるため、確定申告が必要な会社員の方や医療費控除を検討している方の申告の手間が大幅に削減できます。
7. まとめ
年末調整は例年10月から翌年1月にかけて行われ、従業員の提出期限は多くの会社で11月頃に設定されています。提出が遅れると控除が適用されない可能性があるため、早めの準備が大切です。還付・追加徴収は12月または1月の給与に反映されます。また、副業所得の有無や医療費控除・寄附金控除など、年末調整だけでは完結しない場合は、確定申告が必要になる点も押さえておきましょう。スケジュールを前もって把握し、控除証明書などの準備を早めに進めておくことで、年末調整をスムーズに進められます。