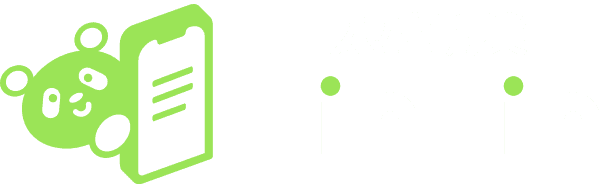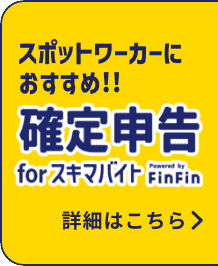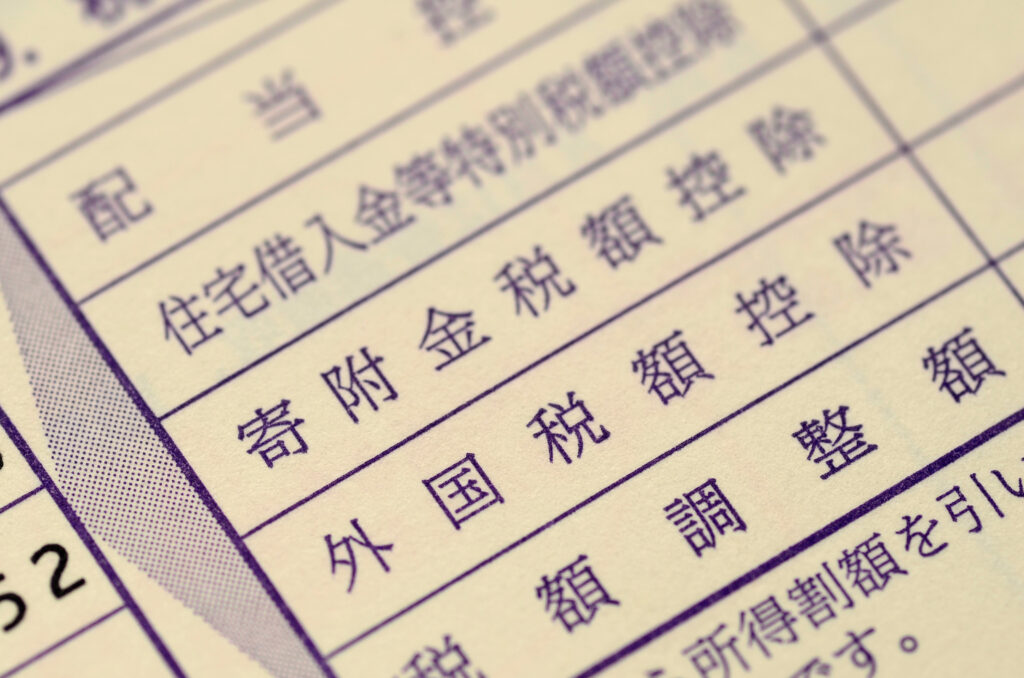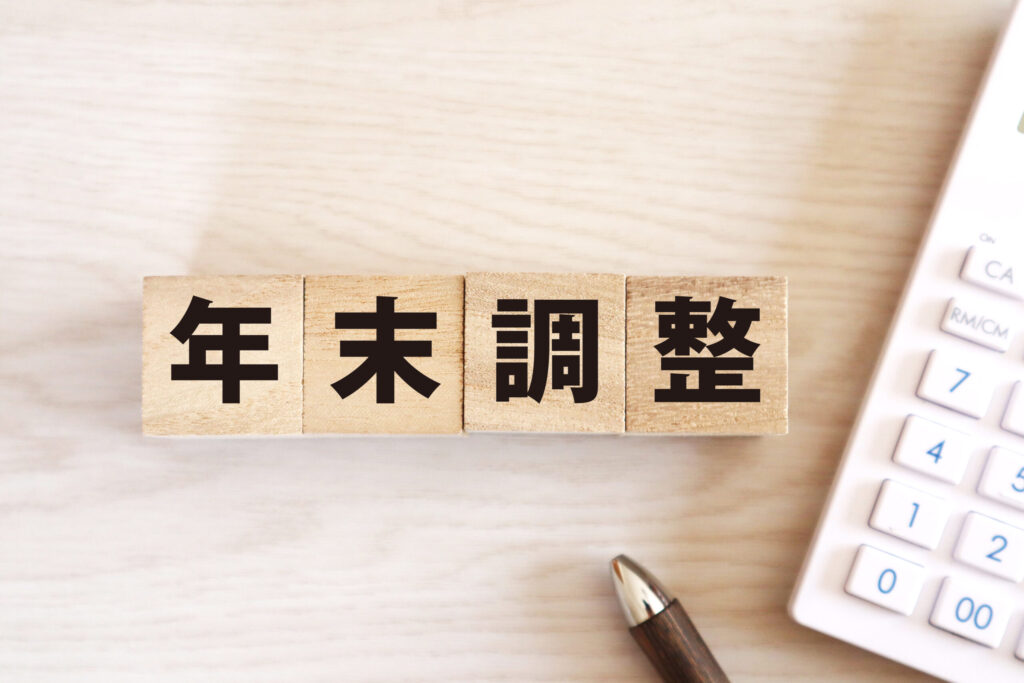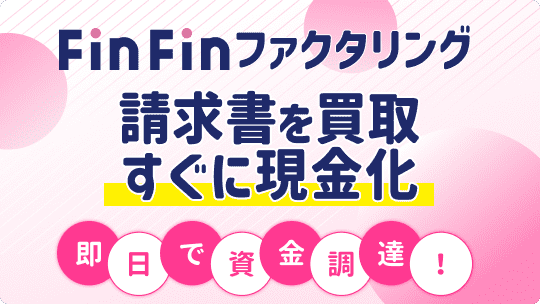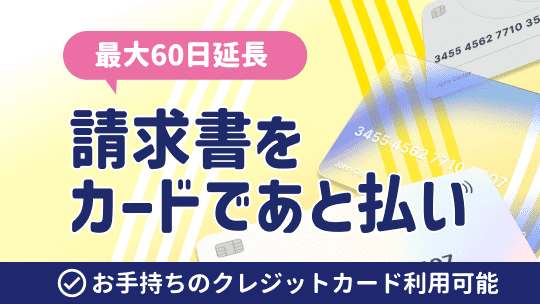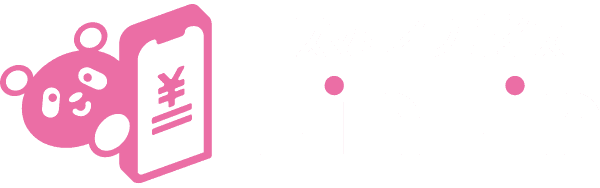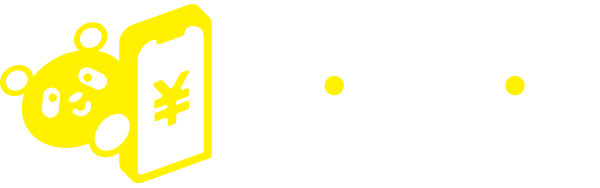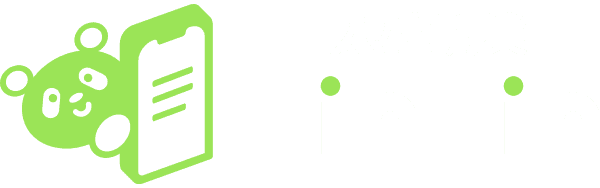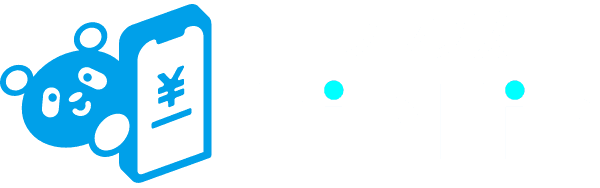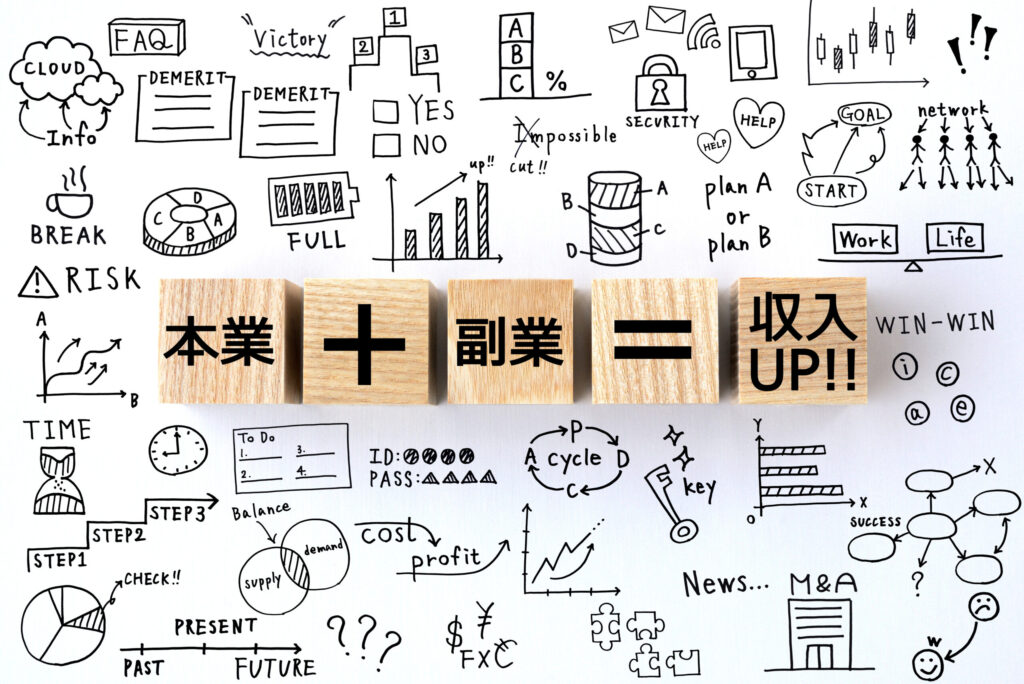
最近は副業の種類も増え、「タイミー」などのプラットフォームを活用することで稼ぐ会社員がたくさんいます。いわゆる「スキマバイト」と呼ばれるものであり、確実に収入を増やせる画期的な方法です。しかし、ここで気になるのが税金の問題。条件によっては「確定申告」を行う必要があります。確定申告は各自で行わなければならないものですが、会社員の場合にはとくに「まったく知識がない」という方も多いでしょう。
今回は、副業でスキマバイトを始めた人で、「自分は税金を納める必要があるの?」「いくらから確定申告が必要になるの?」という疑問を持つ会社員の方々に、申告が必要となる給与額のライン=「申告ライン」について解説します。
目次
1.まず、「確定申告」とは?「年末調整」との違いを理解しよう
確定申告には「所得税の確定申告」と「消費税の確定申告」があります。消費税の確定申告を行うのは一定の事業者のみに限られ、一般的な会社員には不要ですので、この記事においては「所得税の確定申告」についてご説明します。
「確定申告」とは、1年間の所得を合計し、さらに納税額を算出して納税する手続きのことをいいます。「税金なら毎月の給与から天引きされているけれど…」と思うかもしれませんが、それはいわば「仮の金額での納税」です。これを「源泉徴収」と呼びます。
源泉徴収は「ざっくりした金額で納税しておく」というものであり、本来の納税額は、その年が終わってから年間の収入をまとめて再計算しなければわかりません。この再計算を勤め先の会社が行うことを、「年末調整」といいます。年間の給与額が確定する年末でなければ再計算ができないため、年末に行われる……ということですね。
ところが、会社は社外のお金の動きまでを含めて計算することができません。あくまでも、その会社で支払った給与に関するもののみが計算され、個人が副業で稼いだお金については除外されてしまいます。そこで、各個人が最終的な収入や納税額を「確定」し、税務署に「申告」する必要が出てきます。この手続きを「確定申告」と呼びます。
多くの場合、源泉徴収では多めの金額が徴収されるものです。会社員の場合、追加で納税するよりも、還付を受けられるケースが多いものです。つまり、確定申告が「支払いすぎた税金を取り戻すための手続き」になるわけです。
なお、寄附金控除や医療控除などの手続きも「社外のお金の動き」に分類され、年末調整で手続きすることはできません。それらを行う場合にも、確定申告が必要となります。税金を計算する機会が2度あることになりますが、確定申告で上書きされるため問題ありません。たとえば「主な勤め先で保険料控除のための証明書を提出し忘れた」といった場合には、確定申告をすればきちんと控除が反映されます。
2.「申告ライン」は「給与所得20万円超」
所得税の確定申告は、原則、定められた金額を超えて稼いだ場合に確定申告の義務が発生します。主な勤め先で給与を受け取っており、スキマバイトなどの副業を行っている人の場合には、「副業による給与所得が20万円を超える場合」に確定申告が必要です。
なお、一度確定申告をしたからといってそれ以降毎年続けなければならないというものではなく、あくまでも必要がある年だけに行うことになります。
「それでも、確定申告が必要かどうかを自分で判断する自信がない」という方は、会計アプリ「確定申告 for スキマバイト」を活用しましょう。個人情報を入力し、働いている勤め先から交付される源泉徴収票をすべて読み込むことで、その年の確定申告が必要かどうかを判断することができます。「あといくら稼いでも大丈夫か」といった収入の管理も可能ですので、非常に便利です。
3.確定申告は不要でも「住民税申告」は必要
副業の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要ですが、「住民税申告」は20万円を超えない場合であっても必要なので気を付けましょう。確定申告で納税する所得税は「国税」ですが、住民税は「地方税」であり、申告は自治体で行う必要があります。なお、確定申告をすれば住民税の手続きも併せて行われますので、住民税申告は不要です。
申告の方法などは各自治体によって異なりますので、ホームページや窓口で確認してください。申告の際に使う「住民税申告書」のフォーマットも、各自治体が作成しています。
副業をし、確定申告や住民税申告をすることで変化するのが、住民税の金額です。住民税の金額が変わったこと=「その会社の給与以外に別の収入があること」は勤め先にわかってしまいます。副業をしていることを隠したい場合には、自分自身で直接自治体に納付する「普通徴収」を選択する必要があります。もちろん、「なぜ普通徴収にしたいのか」という疑問は抱かれてしまいますので、就業規則で明確に副業を禁じられている場合にはまず相談するほうをお勧めします。
詳しくは下記の記事をご確認ください。
『副業を持つ会社員が確定申告すると、「住民税の申告」で会社にバレる?ポイント解説!』
4.確定申告の申告先や申告方法、期限
■申告先
確定申告の申告先は、事務所や自宅がある住所を管轄とする税務署です。国税庁HPで検索することができます。
国税庁HP 国税局・税務署を調べる
■申告方法
次のような方法を選択することができます。
1.税務署まで行って申告する
2.ソフトなどを使って紙に印刷、あるいは手書きで作成し、税務署まで行って持ち込む
3.ソフトなどを使って紙に印刷、あるいは手書きで作成し、税務署に郵送する
4.e-Taxで申告する(国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」での作成が必要)
5.会計アプリ(スマートフォン)から電子申告する
現在、特に活用されているのはインターネットを利用したe-Tax、およびスマホの会計アプリを使っての電子申告です。よく知らないうちは「税務署に行くのが大変」という印象を持つことが多いと思いますが、オンラインの申告ができれば自宅で完結させることが可能です。
なお、オンライン申請(④と⑤)をする際には、「マイナンバーカード」(2025年7月時点の名称)と、スマートフォンかICカードリーダーが必要となりますのでご注意ください。
■申告する期間、期限
毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日(土日祝日に重なる場合はその翌日)までに申告します。期限の「時刻」については提出方法によって異なるので注意してください。
・税務署に持参…管轄の税務署の営業時間まで
・税務署へ郵送…締切日まで。ただし「消印有効」
・電子申告(e-Tax、アプリ)…深夜24時00分
5.確定申告をするべきなのに、しないとどうなる…?
確定申告と納税が必要な収入がありながら確定申告をしなかった場合には、延滞税や加算税が課されることがあります(追徴課税)。さらに、「わざと納税を逃れようとした」といった場合には、非常に重い税金を追加で課せられる場合もありますので(重加算税)、必ず確定申告をするようにしましょう。税務署はさまざまな方法でお金の動きを把握しています。これを軽く考えてはいけません。
なお、もし「本当は申告が必要だったのに、そうだとは知らなかったのでできなかった」といった場合には、所轄の税務署に相談するようにしてください。いきなり重い税金を課せられることはほとんどなく、どのように対処したらよいのかを丁寧に教えてもらえます。税金を支払う姿勢がある納税者に対して、突然の「お説教」をすることはありませんので、ご安心ください。
6.確定申告はデメリットばかりじゃない!
確定申告は面倒なものですが、正しく行えば税金の還付を受けられることも多く、デメリットばかりの手続きではありません。複数の勤め先で源泉徴収されている場合には、それなりに多くのお金が戻ってきます。今回の記事で「どうやら確定申告をしたほうがいいようだ」と思った方は、まずは現時点での所得の確認や、役立ちそうなアプリの導入などから初めてみてくださいね。
副業での収入アップは、この物価高のなかでも心にゆとりができるだけでなく、普段とは違う仕事ができることで意外なストレス解消になったり、コネクションを増やしたりすることができたりと、別のメリットもたくさんあります。また、新たなビジネスを知ることで、ご自身の人生そのものを変えていくきっかけになるかもしれません。税金についても少しずつ勉強しながら、無理なく続けていきましょう。
【スマホで簡単】FinFinを使って確定申告をしよう
スキマバイト、スポットワーク、複数のアルバイトをしている皆さんにおすすめしたいのが、「確定申告 for スキマバイトPowered by FinFin」です。こちらのアプリでは、アルバイトの収入を管理し、年収の壁が一目でチェックできるだけでなく、確定申告の手続きも簡単にサポートしてくれます。特に確定申告が必要なスポットワーカーにとって、便利で頼りになるツールです。働き方をもっと自由に、そしてスムーズにするために、ぜひチェックしてみてください!
記事監修者紹介

天野大 先生 天野大税理士事務所
1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。